今回は『国語が苦手な理系大学受験生|最短で共通テスト(センター試験)で7割を取るための勉強法』について紹介します。
大学受験の理系選択者のうち、国語が非常に苦手という人は少なくないと思います。
私も、過去に模試で200点中38点という結果を叩き出したことがあるほど、国語が苦手でした。
しかしそんな私でも、マーク模試やセンター試験(共通テスト)で140点は取れるようになりました。
理系の大学受験生にとっては、国語はいかに時間をかけずに『足を引っ張らない程度』にするかが重要です。
 マネー金
マネー金
国語のセンスがない理系受験生は時間をかけるだけ無駄

- 国語が苦手な理系大学受験生が7割より上を目指そうとすると、かなり時間がかかるのでオススメしない
【筆者の経験談】
私は、ネットで調べた国語の勉強法を駆使したところ、140点台まで上げることができました。
今まで100点も越えなかったり、38点という驚異の結果を叩き出したりしていたので、自分でも驚きました。
そして、さらに点が伸びることを期待して、他の科目の勉強時間を削りながら国語の勉強を続けました。
しかし、その後どんなに勉強時間を増やそうと、点は一切伸びませんでした。
最終的に、7割台(140点台)を超えるまでにかかった時間の2倍の時間を費やしたのですが、変わりはありませんでした。
もしこれで受験に落ちていたら、私は国語に無駄に勉強時間を費やしたことをずっと悔やんでいたことでしょう。
理系の受験生の場合、医学部・東大・京大志望以外は必要以上に国語に時間をかけるメリットはありません。
7割台(140点台)を取ることができれば上出来です。
あとは2次試験でも必要な英語、数学、理科2科目で十分補うことができます。
そのため、最短で国語で7割を取れるようにして、あとは2次でも必要な科目に時間を費やすことをオススメします。
ちなみに、私がいくら国語に勉強時間を費やしても8割の壁を越えられなかった最大の原因は『速読力の無さ』です。
もし、文章を読む速度にあまり自信がないのであれば、国語から早めに手を引いた方が良いかもしれません。
最短で国語の点を7割にするための勉強時間と勉強順

【国語の勉強時間】
- 1日2.5時間 × 40日 = 100時間
【国語の勉強順】
- 古文(65時間)〔目安34点〕
- 漢文(20時間)〔目安48点〕
- 評論(15時間)〔目安30点〕
- 小説(0時間)〔目安30点〕
国語の勉強は『夏休み』か『共通テスト(センター試験)直前』がオススメです。
夏休みは普段よりも勉強時間が多めに取れるので、国語に時間を配分しても大丈夫です。
ただ、夏休みに国語の勉強をする場合、せっかく夏休みに勉強した内容を本番前に忘れてしまいかねません。
そのため、夏休みに国語の勉強をする場合は、『文法』を中心に学ぶようにしましょう。
そして、直前期で一気に『単語や構文の暗記』をするようにしましょう。
理系受験生の場合の国語の勉強順は『古文→漢文→評論→小説』の順で学ぶのがオススメです。
古文と漢文はどちらを先に学ぶべきかでよく議論されていますが、基本的には古文から学ぶことをオススメします。
なぜなら、漢文では古文の単語や用法の知識を一部利用するからです。
ただ、古文と漢文の両方を勉強する時間がないという人の場合は、漢文を最優先して勉強してください。
最悪の場合、漢文は構文の丸暗記で点数を取ることができます。
古文から学ぶことをオススメするのは、『漢文で安定して点を取るためには一部古文の知識が必要』というだけの理由です。
評論と小説に関しては、時間がある人だけでいいです。
多少の時間で対策をして点数が上がるのは評論だけです。
小説に関しては、理系受験生がかけることのできる勉強時間では大して変わりません。
そのため、まずは古文漢文を集中的に学習しましょう。
『古文→漢文→評論』の一通りの対策を100時間ほど行なえば、7割台(140点台)は超えます。
最短で共通テスト(センター試験)の国語の点数を7割にする勉強法
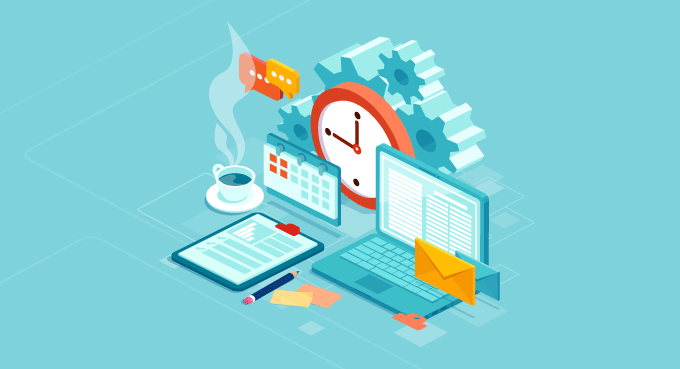
ここでは、実際の共通テスト(センター試験)の国語の勉強法を紹介します。
古文
【古文の勉強法】
- 古文単語を参考書で丸暗記
- 動詞の活用や用法などの文法を暗記(基本活用、助動詞、敬語のみで良い)
※助動詞は「受け身」「使役」「希望」「比況」はやらなくていい
※終われば過去問演習をする。古文の過去問を解く時は『設問→本文』の順に見てから問題を解く
古文は必要事項を丸暗記すれば、少なくとも35点以上は取れます。
英語や漢文とは異なり、読む順番がバラバラというわけでもないので、単語や重要な用法さえ知っていれば読むことができます。
そのため、まずは『古文単語』と『活用などの用法』を暗記しましょう。
単語は単語帳で暗記で良いです。
文法に関しては、敬語と助動詞の項目だけの演習で大丈夫です。
基本的にはそれらだけでも40点を取る知識はついています。
ただ、古文は年によって難しさが大きく異なります。
通常のレベルであれば文章を自分で読み進めることができますが、難しくなると一切意味が分からなくなります。
そういう場合に役立つのが、設問から読んで内容をまず想像しておくことです。
内容を想像したうえで読み進めていくのと、内容が一切分からないままで読み進めていくのではかなり違います。
そのため、古文の場合はまずは設問を読んでから本文を読む練習をしておきましょう。
漢文
【漢文の勉強法】
- 漢文で頻出の構文を参考書で全て丸暗記するだけ
※暗記が終わって時間が余れば過去問で問題演習
漢文はこの参考書に載っている構文を丸暗記するだけで最低でも40点は取ることができるようになります。
さらに過去問演習して、間違えた問題を復習すれば、ほぼ満点を安定して取ることができるようになるでしょう。
私はこの参考書のおかげで、今まで捨てていた漢文で40点を下回ることが無くなりました。
評論
【評論の勉強法】
- さらっと評論の解き方の解説を見るだけで良い
※それ以上時間をかけても、それほど変わらない
評論はさらっと上記の参考書で解き方を見るくらいで良いです。
理系受験生の国語の勉強量で演習をがっつりしたところで、大して点数は変わりません。
そのため、本文と設問をさらっと確認した後は、解答をすぐに確認して解き方のフレームを理解しましょう。
小説
- 対策する必要なし
小説こそ理系は対策する必要がありません。
難しさによって点がかなり左右されますし、安定もしません。
それよりも、古文漢文に時間をかけましょう。
これで合計140点は取ることができるようになります。
まずは80時間ほど時間をかけて試しに勉強してみてください。


