今回は『理系は共通テストで地理B選択?点の取れる勉強法と取れない勉強法』について紹介します。
地理Bは他の社会科目に比べると、資料読み取り力や論理的思考力が必要と言われています。
そして、理系は比較的これらの能力が高いため、地理との相性がいいとされています。
しかし、実はこれが罠なのです。
理系の中でも、地理Bに向いている人と向いていない人がいるので気をつけてください。
 マネー金
マネー金
筆者が共通テスト地理Bで点が取れなかった話
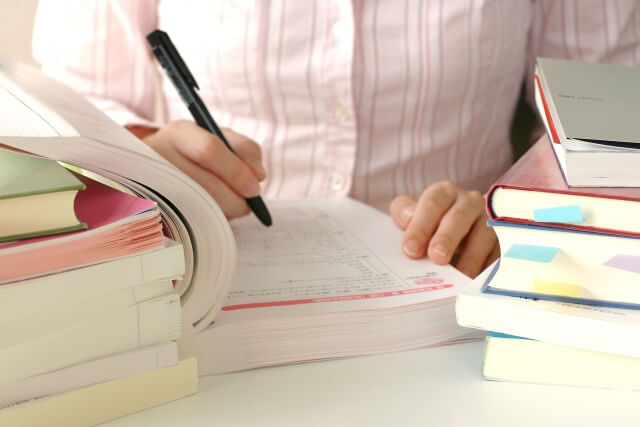
- センター試験(共通テスト)対策中のほとんどの時間を地理Bに費やしたが50点台を抜け出せなかった
私は理系選択者であり、当然のように地理Bを選択していました。
ある程度の知識をインプットすれば、あとはもともと持っている分析力で簡単に高得点を取れると思っていたからです。
私は、理系にしては多すぎると思われるくらい地理Bに勉強時間を取っていました。
当然、暗記すべき事項や基礎知識は抜かりなく定着するまで繰り返し復習していました。
資料の読み取りや地図の読み取りも苦手ではありませんでした。
しかし、模試やセンター試験(共通テスト)で一度も50点台を抜け出すことができなかったのです。
普通の科目の場合は、参考書などで基礎を固めた後に演習を繰り返せば、効率よく成績を上げられるのですが、地理に通用しませんでした。
おそらく、地理にかけた時間を日本史や世界史などに費やしていれば、もっと高得点を取ることができたでしょう。
地理Bに向いている人と向いていない人の特徴

地理Bで高得点を取れる人と取れない人には特徴があります。
地理Bに向いている人
- 地理が好きな人
- 参考書演習よりも実践演習を大切にしている人
- 社会に勉強時間を費やしたくない人
- 社会で高得点を取らなくてもいい人
地理は点数が安定しやすい科目と言われています。
一般常識や資料読み取り問題も比較的含まれているので、勉強をあまりしなかったとしても50点台を取ることができます。
一方で、日本史や世界史などの暗記量に左右される科目の場合、勉強していなければ点数を取ることができません。
このように、地理は点数が伸びにくい一方で、勉強をしなくてもある程度点数を取れるという特徴があります。
そのため、社会でそれほど高得点を取る必要のない人や、社会に勉強時間をあまり費やしたくない人には向いている科目と言えます。
また、参考書演習は基本的に”知識をインプットする勉強法”です。
一方で実践演習は”出題問題の傾向を把握&知識をアウトプットする勉強法”です。
当然、日本史や世界史の場合は、幅広い基礎知識がなければ話にならないので、参考書演習が重要になります。
一方で地理の場合、参考書の知識が必ずしも使えるとは限りません。
それよりも、実践問題で出題傾向や類題を繰り返し解いて慣れることの方が大切です。
私のように、『基礎を固めてからでないと実践演習はしたくない』 という性格の人は、地理よりも日本史や世界史の方が向いています。
真面目な完璧主義タイプの性格の人が地理を選択すると、努力量と点数が比例せずに苦しむことになるかもしれません。
地理Bに向いていない人
- 地理が好きではない人
- 実践演習よりも参考書演習を大切にしている人
- 社会に時間を費やしてもいい人
- 社会で高得点を取らないといけない人
先ほど説明したように、地理は努力量に比例して点数が伸びるとは限りません。
勉強方法が合っていなければ、かなりの努力量を注ぎ込んでも大した成長が見られないということも起こり得ます。
一方で日本史や世界史の場合、勉強時間をかければそれだけ点数は伸びます。
そのため、真面目で努力家な人や、社会に勉強時間を費やせる人は、地理よりも他の社会科目を選んだ方が点数は取りやすいでしょう。
地理Bの点の取れる勉強法と点の取れない勉強法
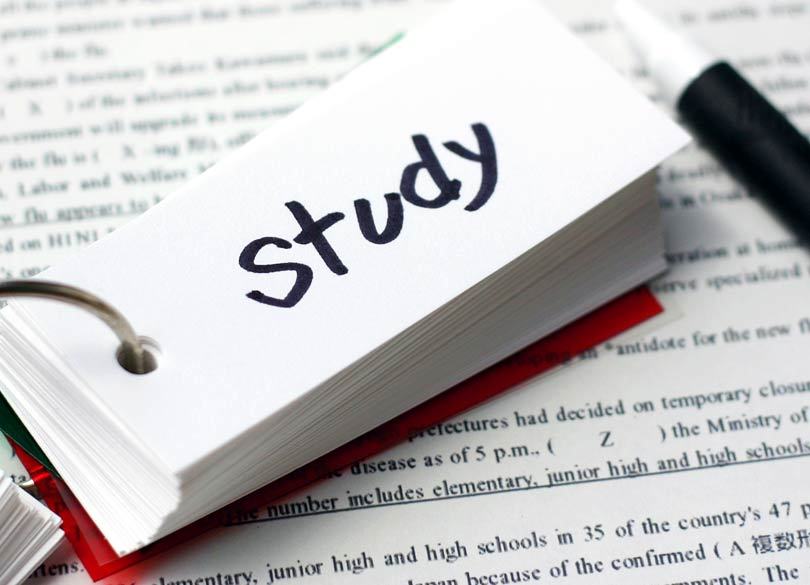
ここからは、すでに地理選択をしていて後に引けない人向けです。
点の取れない勉強法
- 参考書や教科書を反復して基礎知識を定着させる
- 予備校が出している予想問題集の実践演習
- 実践演習の答え直しと間違えた問題の反復
用いた教科書
用いた参考書
用いた実践問題集
上記は点数を取れなかった私の地理の勉強法です。
一見すごく良い勉強法に見えますが、地理に関してだけ言えば非常に無駄の多い勉強法です。
暗記に多くの時間をかけてしまい、実践演習にかける時間が減ってしまったからです。
普通の勉強の場合とは異なり、地理の場合は如何に実践をこなすかが重要になってきます。
点の取れる勉強法
- 参考書や教科書にさらっと目を通す
- センター試験(共通テスト)の実践演習
- 答え直しの際に、参考書や教科書を辞書的に利用して知らない知識を調べる
- 一通り直し終えたら再び同じテストを2回解き直す
- それでも解けない問題があれば、その問題をコピーしてノートに貼り付ける
- それが終われば新しい問題で実践演習
用いた教科書
上に同じ
用いた参考書
上に同じ(一問一答 地理Bターゲット2200は無し)
用いた実践問題集
上記は勉強時間が少ないのに90点台をキープしていた友達の地理の勉強法です。
地理は知識の暗記よりも実践が重要と言いましたが、流石に知識ゼロでは意味がありません。
しかし、かといって完璧に覚える必要もありません。
そこで、最初は参考書を1周分さらっと読んで、全体の流れや知識をボヤっと頭に入れておきましょう。
そして、その上で実践演習を行ないましょう。
ここで重要なのは、予備校が出している実践問題集ではなく、共通テスト(センター試験)の過去問集で演習を行なうことです。
予備校が出している予想問題集と過去問では難易度が異なります。
そして、過去問を演習すれば、出やすい問題の傾向を把握することができます。
そのため、実践演習には共通テスト(センター試験)の過去問を用いましょう。
また、演習が終わったら必ず時間をかけて答え直しをしましょう。
その際に重要なのが、答え直しの際に出てきた知らない知識は、参考書や教科書で調べて確認しましょう。
つまり、参考書や教科書は辞書的な使い方をするということですね。
答え直しが終われば、さらに2度ほど同じ過去問を解き直してください。
それでも解けない問題があれば、その問題をコピーしてノートに貼って自分だけの弱点問題集を作りましょう。
共通テストとセンター試験の地理Bの違い

- センター試験と共通テストでは問題構成にほとんど差はない
違いがあるとすれば、共通テストの方がセンター試験よりも資料や地図データ読み取りの問題が多いということですね。
そのため、センター試験以上に『知識の暗記』が点数に直結しづらくなります。
まだ社会科目の選択をしていない理系の高校生は、もう一度ほど社会科目の選択を考えてみてください。
そしてすでに地理を選択している人は、地理の勉強の仕方を見直してみてください。
多くの時間をかけたのに50点台から抜け出せなかった私のようになると悲しいですからね。


