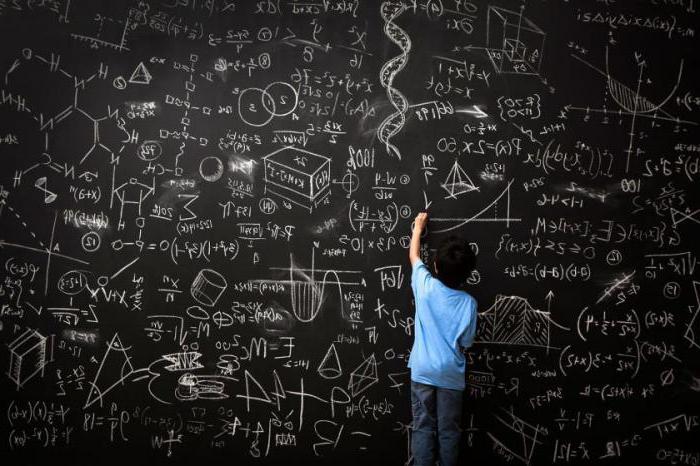今回は『【理系】数学が苦手な人向けの青チャートの使い方|3か月で共通テスト8割』について紹介します。
「理系なのに数学ができない」と悩んでいる人も少なくないでしょう。
しかし、正しくチャート式を使うことができれば、数学がどんなに苦手でも共通テストで8割以上はかならず取れます。
もし勉強しているのに成績が悪いのであれば、それは勉強方法が間違っている可能性が高いので、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。
青チャートで使う項目はたったの4つ
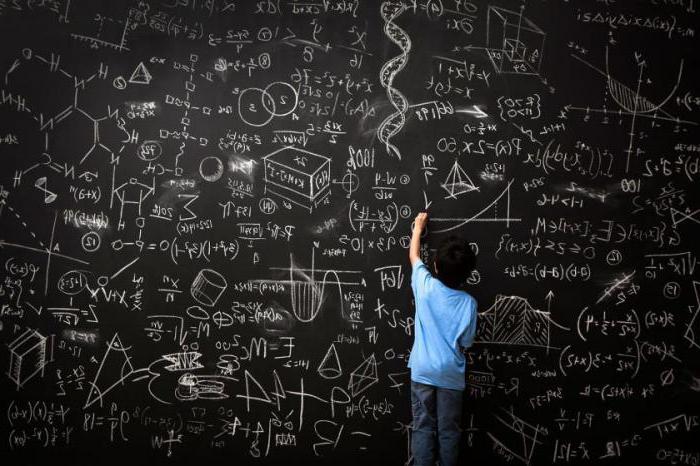
- 公式や原理の紹介ページ
- 例題問題★1〜★3
- 回答の指針
- 問題の解説
※★3が難しければ★1〜★2を解く
公式や原理の紹介ページ

その単元で使われる「公式」「定義」や、原理を詳細に紹介しているページであり、各単元の最初についている
例題問題★1〜★3

青チャート右上の★1~★3の「例題問題」をメインで解く(※練習問題やexerciseはやらなくてOK)
回答の指針

その問題を解くためのきっかけとなる考えを記した箇所であり、問題を解く戦略の立て方を学べる
問題の解説

青チャート(ほかのチャート式)で使う項目は上記4つのみで、それ以外は一切使いません。
数学が苦手な人向けの青チャート演習

①公式や原理の解説ページを読む
これは、スポーツでいうところの「最低限のルールをイメージできるようにする」段階です。
たとえばテニスであれば、相手のコートにボールを打ち返して、ノータッチを取れば自分に点が入るみたいなイメージ。
この「最低限のルール」がボヤッとでもイメージできていれば、ルールに従うために自分がなにをすべきかの判断がしやすくなるので、問題の解く時の方針が立てやすくなります。
たとえば、強く打つか、それとも相手のいないところに打つか、みたいにルールに従う中で立てるべき戦略が思いつきやすくなるのです。
②公式や定義のページを確認しながら問題を解く
問題を解く時に、公式や定義がまだ定着していないことも多いと思います。
これらは、先ほどのテニスの例でいう、「ドロップショット」「ボレーショット」などの打ち方に近いです。
相手のいないところに打つ、強めに打つ、などの戦略が立ったとしても、その球の打ち方が分からなければ意味がありません。
その「打ち方」を知って初めて、自分の描いたイメージを実現できるので、慣れないうちはお手本を真似しながら進めていく必要があります。
③解き方が分からなければすぐに解答を見る
- 特に1, 2周目は解答を理解することよりも暗記することを意識する
たとえば、テニスのプロの試合を見ていて、「え?なんでそこに打ったの?」と思う時ありませんか。
「相手のいないところに打つ」というセオリーから外れて、相手のいるところに打ったりする場面、一度は見たことがあると思います。
ほかのスポーツでも、一見すると訳がわからないプレイがあったりしますが、実際は相手に効果的であったりします。
これは、「こうすると相手が怯む」という1つの攻撃パターンで、いわゆる解法の1つみたいなものです。
そのため、最初は分からなくて当然で、何度もパターンをすり込ませることで、あのようなゲームメイクができているのです。
これは数学でも同じで、たとえ東工大に受かるような人間であったとしても、最初は基礎問題ですら意味が分かりません。
ですが、解法を暗記して使ってを繰り返しているうちに、徐々に意味が分かってきて、使いこなすことができ始めるのです。
④答え合わせをする
- 自分で解けた場合:○
- 何かを参考にして解いた場合;△
- 参考にしても解けない場合:×
⑤最後まで演習して2, 3周反復する
- 最初の参考書が青チャートの場合は、例題★1〜★3すべてに〇が3つついた状態になるまで反復
※2冊目以降の参考書は1度自力で解けた問題は2度とやらなくてOK
ここまでできれば、共通テストでいう8割以上を取ることができます。
最初に1度解けたからといって安心していると、しばらくして解けなくなっていることがほとんどです。
そして、”この問題はもうできるはず”という勘違いのまま進んでいき、基礎が固まってもいないのに、できていると思い込んでしまうケースに陥ってしまいます。
こうなると、偏差値を60以上にまで伸ばすときに、他人の何倍も時間がかかってしまいます。
今までにいろんな生徒を見てきたのですが、このケースに当てはまる人が非常に多く、さらに厄介なのが「自分は当てはまっていない」と思っている人がほとんどです。
そのため、いま一度、自分は基礎力がついてないと言い聞かせながら、チャート式を丁寧に仕上げるようにしましょう。