今回は『受験で大学の過去問を解く暇がない?実は過去問を解かない方が合格率が上がる』について紹介します。
大学受験期間中は参考書の勉強などで時間が取られてしまい、なかなか過去問を解く暇がありませんよね。
私が受験生の時も、過去問を初めて開いたのはセンター試験(共通テスト)直後でした。
時間的余裕がない人の場合、過去問の扱いには注意が必要です。
過去問は『使い方』と『時期』を誤れば、逆効果となる可能性が非常に高いからです。
そこで今回は、余裕がない中で過去問を最大限に活用する方法について紹介したいと思います。
志望大学の過去問を解かない方が合格可能性が上がる理由

- 時間に余裕がない人の場合、大学の過去問を解く時間を基礎固めに使った方が有益
なぜ志望大学の過去問を解く暇があったら基礎を固めるべきなのでしょうか。
過去問演習よりも基礎固めをするべき理由
- 大学過去問の構成
- 大学の過去問演習にかかる時間
それぞれについて以下で説明します。
1.大学過去問の構成
- わざわざ不便な大学過去問を解く必要性が一切ない
大学の過去問は、基本的にどの大学でも以下のような構成をしています。
【大学過去問の構成】
- 基礎問題:40%
- 標準問題:20%
- 応用問題:20%
- 超応用問題:20%
この各問題の難易度のレベルは大学ごとに異なりますが、基本的にはどの大学も上記のような構成で入試を組んでいます。
『基礎問題』『標準問題』
- 参考書演習がしっかりできていれば解けるように設定されている
超難関大であったとしても、『基礎問題』『標準問題』は参考書演習ができていれば解けるように設定されています。
つまり、基礎力という土台が安定していれば『合格』は十分狙うことができるのです。
『応用問題』『超応用問題』
- 参考書では見たこともないような特殊な問題が出題されることが多い
一方で『応用問題』『超応用問題』は奇問であるケースが非常に多いです。
特に、志望大学のレベルが上がれば上がるほど、参考書などでは見たこともないような特殊な問題が出題されます。
毎年大学の教授が面白半分で特殊な問題を出したりもするので、正直どんな問題が出るか予想できません。
そのため、『応用問題』『超応用問題』に関しては、割と運次第なのです。
もし志望大学の合格可能性を上げたいのなら、『基礎問題』『標準問題』を確実に解けるようにする必要があります。
市販の参考書の方が網羅的に『基礎問題』『標準問題』を掲載しているので、効率よく学ぶことができます。
2.大学の過去問演習にかかる時間
- 得るものが少ない過去問演習に貴重な勉強時間を割くのはもったいない
大学の過去問の1年分の時間割を以下としましょう。
【大学過去問の1年分の時間割】
- 1教科当たりの時間:60分~120分
- 教科数:4~5教科
- 計:240分~600分
ここにさらに答え合わせと解説の確認時間が入るので、ほぼ丸一日あるいはそれ以上かかることになります。
解説を理解して解けるようにするとなると、さらにプラスで2日ほどかかるでしょう。
そうなると大学の過去問演習1年分だけで、最低でも3日以上失うことになります
それで大きな成長ができればいいのですが、実は過去問演習ではそれほど得られる物はありません。
なぜなら、過去に一度出た問題はもう二度と出ない上に、『基礎問題』『標準問題』以外は奇問だからです。
入試直前期に過去問演習で勉強日数を失った時の損失は非常に大きいです。
ただでさえ滑り止め等の入試で時間が取られる上に、過去問にまで時間を奪われてしまうと、自分の勉強時間が無くなってしまいます。
大学過去問の効率的な活用の仕方
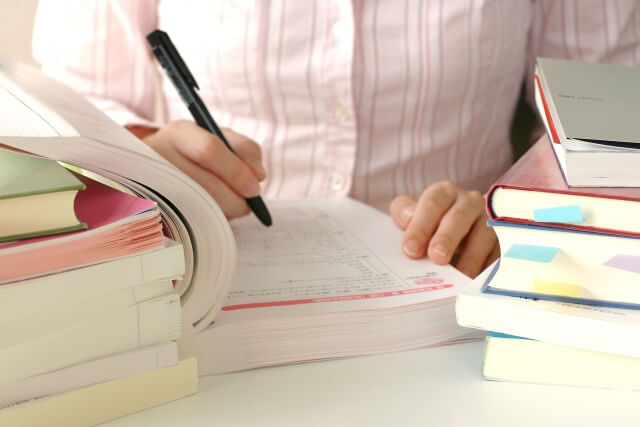
ここでは過去問の効率的な活用の仕方について紹介します。
志望大学の過去問の活用の仕方
- 問題の形式の把握
- 出題される単元の傾向を把握
- 問題によく使用される表現や公式の把握
1.問題の形式の把握
- 過去問を開いて、各教科の1年分の問題にさらっと目を通す
- 問題の出題形式をザっと把握する
まずは過去問の各科目の1年分の問題にさらっと目を通してみてください。
【例えば英語の場合】
- 大問の数(その中の小問の数)
- 大問の配点(小問の配点)
- ざっと見た感じの各大問の難易度
- 難易度を考慮した各大問(小問)の時間配分の目安
- 「精読問題」「速読問題」「英作文問題」「選択肢問題」等の出題割合確認
基本的には英語以外の科目も上記の英語の例と同様です。
1年分さらっと見終わったら、さらにもう2年分過去にさかのぼって確認してください。
こちらに関しては、あくまで年ごとに出題形式が変わっていないかの確認作業程度なので、本当にさらっとで良いです。
2.出題される単元の傾向を把握
- 過去問の目次を全て確認して各年度の出題単元を確認する
- 実際に各教科の各年度の問題文をさらっと見てみる
過去問には目次がついており、その目次には各年度の各教科の出題単元が掲載されています。
その目次の出題単元を、10~15年分見てみましょう。
そして、3~4年以上出ている単元ならば、警戒しておいた方がいいです。
また、その単元の中の『どんな問題』が出ているのか、実際に問題文をさらっと読んで把握しておきましょう。
3.問題によく使用される表現や公式の把握
- 各年度の問題文と解説に目を通してどのような表現や公式が使われているか把握
- 数年度分見てみて、度々使われている表現や公式を把握
こちらに関しては、『応用問題』『超応用問題』のみで結構です。
問題文と解説を読んで、どのような表現や公式が使われているのかを確認しましょう。
多々使われている表現や公式があれば、その大学は再びそれらを用いた問題を作る可能性が高いです。
例えば、「あの大学の数学は”区分求積法”と”コーシー・シュワルツの不等式”が大好き」みたいな感じですね。
志望大学以外の過去問の活用の仕方
- 志望大学の偏差値±3~4の大学の過去問も先ほど同様に確認すること
大学は入試問題を作る時に、自分の大学と偏差値が近い大学の問題を参考にすることが多々あります。
そのため、偏差値が近い大学は似たような問題が出ることが多いです。
そのため、自分の志望大学の偏差値±3~4の大学の過去問もさらっと見てみて、自分の大学の問題の出題傾向と似ている大学を見つけましょう。
例えば、東大と東工大と早稲田は問題の性質が似ており、京大は慶応と似ています。
そして、もし時間と基礎力に余裕があるのであれば、志望大学と性質が似ている大学の過去問演習をしてみてください。
もしかしたら、入試本番で類題が出るかもしれません。
志望大学の過去問の効率的な活用まとめ
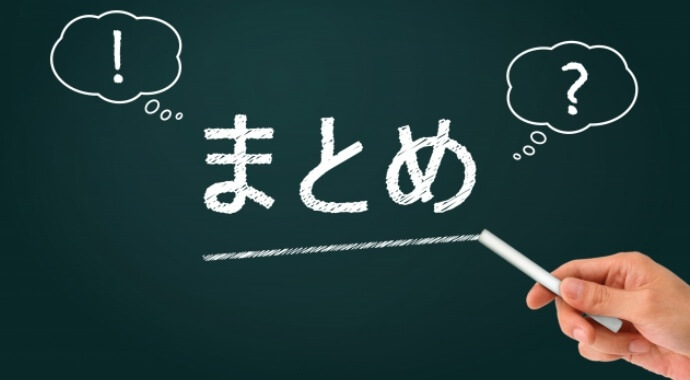
【過去問を解かない方がいい理由】
- 過去問は奇問が多いので演習には不向き
- 学ぶものが少ない一方で、解くと多くの時間が奪われる
【過去問をさらっと確認する方法】
- 問題の形式の把握
- 出題される単元の傾向を把握
- 問題によく使用される表現や公式の把握
志望大学の傾向と単元、頻出の表現や公式等が把握できれば、合格可能性を大幅に上げることができます。
このように、出題範囲を絞り込みながら効率的に進めていかないと、時間に余裕がない人の場合は周りに追いつけません。
成績が志望大学にまだ追いついていないという方は是非活用してみてください。


